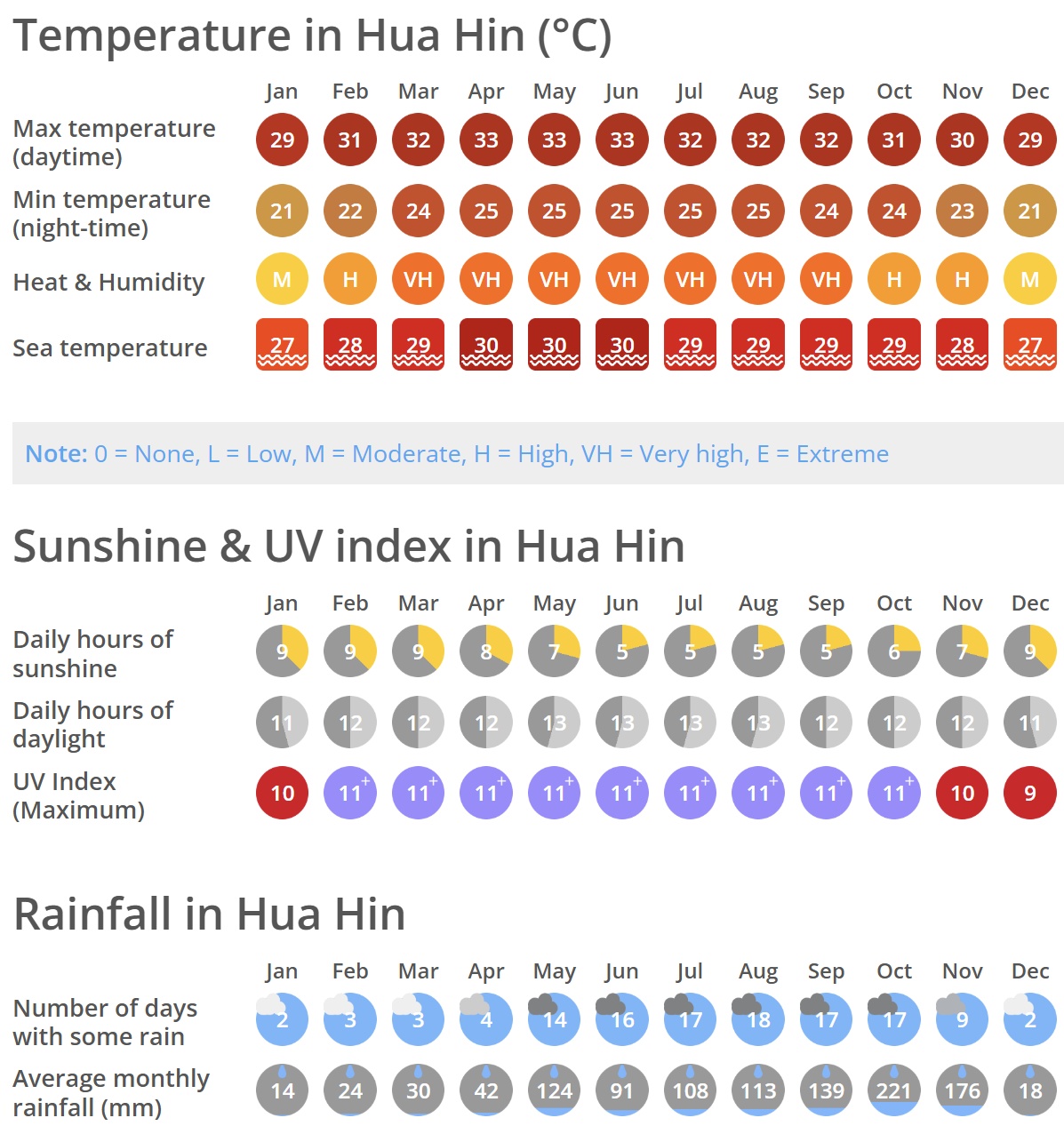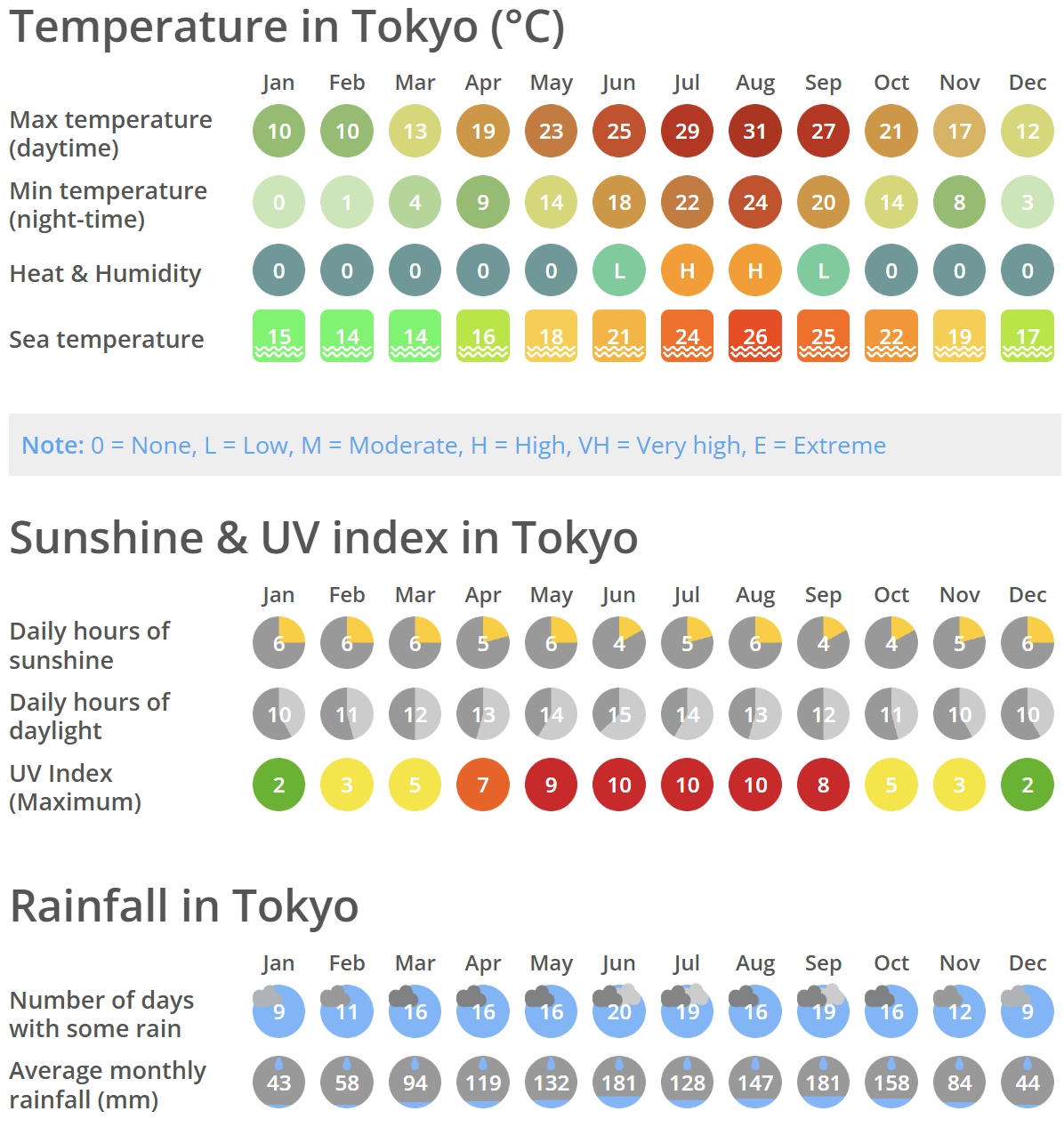2026 National Defense Strategy
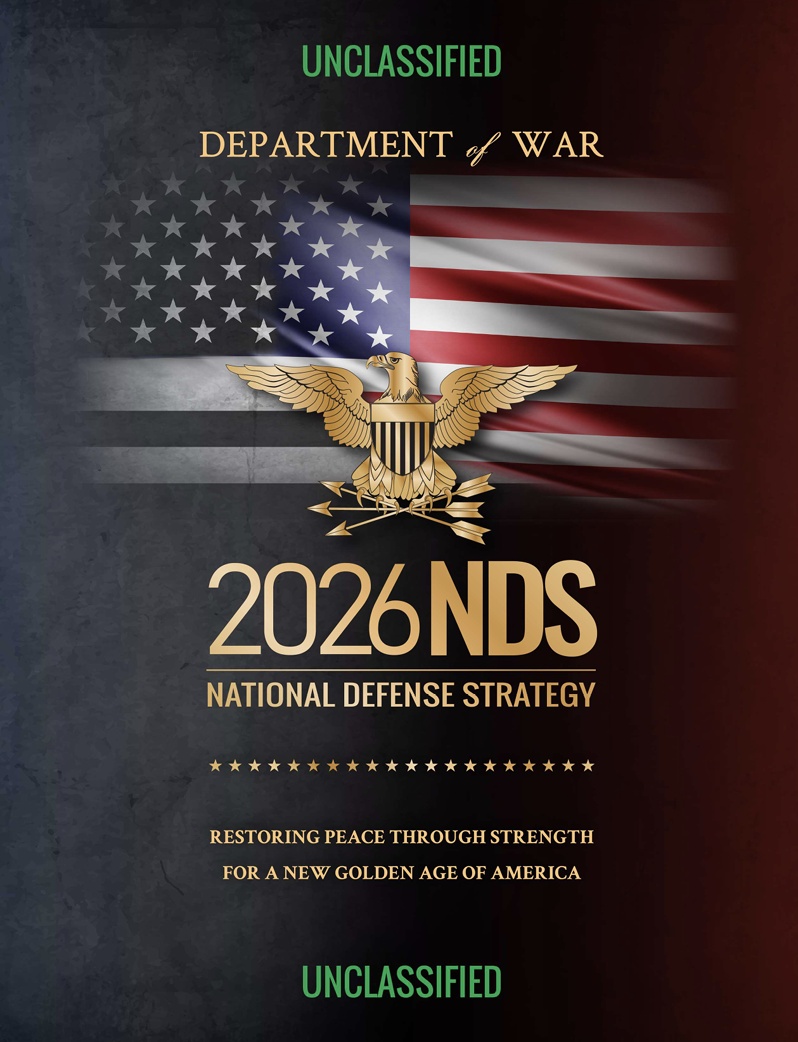 We will build, posture, and sustain a strong denial defense along the FIC. We will also work closely with our allies and partners in the region to incentivize and enable them to do more for our collective defense, especially in ways that are relevant to an effective denial defense. Through these efforts, we will make clear that any attempt at aggression against U.S. interests will fail and is therefore not worth attempting in the first place. That is the essence of deterrence by denial.
We will build, posture, and sustain a strong denial defense along the FIC. We will also work closely with our allies and partners in the region to incentivize and enable them to do more for our collective defense, especially in ways that are relevant to an effective denial defense. Through these efforts, we will make clear that any attempt at aggression against U.S. interests will fail and is therefore not worth attempting in the first place. That is the essence of deterrence by denial.
In this manner, DoW will provide the military strength for President Trump’s visionary and realistic diplomacy, thereby setting conditions for a balance of power in the Indo-Pacific that allows all of us—the United States, China, and others in the region—to enjoy a decent peace. At the same time, in the process of erecting a strong denial defense along the FIC, DoW will ensure that the Joint Force always has the ability to conduct devastating strikes and operations against targets anywhere in the world, including directly from the U.S. Homeland, thereby providing the President with second-to-none operational flexibility and agility.
Software as a service (SaaS) ⇒ Service as a service (SaaS) ?
Services make up over 72% of U.S. GDP. Globalisation, digitisation, and labour market evolution have all conspired to favour services over products in the grand scheme of the economy. In software, the first wave of servicification came with SaaS, but look closely and the mirage of services is dispelled, revealing underneath it nothing more than a billing model change. When Adobe ended perpetual licenses for Creative Suite in 2013 and moved to Creative Cloud, it didn’t change the product, only how you paid for it. Microsoft Office followed suit, with the entire industry doing the same soon enough.
Behind the SaaS, we’re still paying for tools users have to learn, manage, and operate, just now the product is rented monthly. SaaS is service in name, product in nature and all-round ARR-machine in intent.
Donald Trump’
Mark Carney (Prime Minister of Canada)
Over the past two decades, a series of crises in finance, health, energy and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons, tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited.
You cannot live within the lie of mutual benefit through integration, when integration becomes the source of your subordination.
The multilateral institutions on which the middle powers have relied – the WTO, the UN, the COP – the architecture, the very architecture of collective problem solving are under threat. And as a result, many countries are drawing the same conclusions that they must develop greater strategic autonomy, in energy, food, critical minerals, in finance and supply chains.
And this impulse is understandable. A country that can’t feed itself, fuel itself or defend itself, has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself.
But let’s be clear eyed about where this leads.
A world of fortresses will be poorer, more fragile and less sustainable. And there is another truth. If great powers abandon even the pretense of rules and values for the unhindered pursuit of their power and interests, the gains from transactionalism will become harder to replicate.
Hegemons cannot continually monetize their relationships.
Allies will diversify to hedge against uncertainty.
They’ll buy insurance, increase options in order to rebuild sovereignty – sovereignty that was once grounded in rules, but will increasingly be anchored in the ability to withstand pressure.
日本の偽りの礼儀正しさ(小紅書への投稿)
この感覚をどう表現すればいいのだろう。まるでみんながそれぞれ透明なガラスのカプセルに入っていて、互いに姿は見えるし、表面上は丁寧にあいさつもする。でも、一生かかっても相手のカプセルの中に入ることはできない。そんな感じだ。
「今度ご飯行きましょう」というのは「もう二度と会わない」ということ。もし本気にして「いつ空いていますか?」と聞くと、相手はニコニコしながら内心「この人、空気読めないな」と思うのだ。
日本人の笑顔は「半永久メイク」みたいなもの。この笑顔は「仕事上の必要性」によって作っているだけであって本当にうれしいからではない。彼らは、心の中で何万回もこちらをののしっていても、表情一つ変えずに丁寧にお辞儀をすることができる。
日本で「他人に迷惑をかけない」という言葉の意味は「あなたも私に迷惑をかけるな」という含意がある。この極端なまでの境界意識は、確かに生活を便利にするものではあるが、同時に本当に息苦しい。転んでも誰も助けてくれないかもしれない。つらくても誰も声をかけてくれないかもしれない。みんながみんな、「他人に迷惑をかけない」ことに必死だからだ。
傲慢な者は傲慢さが極みに達した時に没落する(ハメネイ師)

In a televised speech from Tehran on Thursday, on the occasion of the anniversary of 1977 uprising against the Shah’s regime, Khamenei said: “As for that one (Trump) sitting there in his arrogance, speaking as if he judges the entire world, let him know that tyrants and oppressors throughout history – like Pharaoh and Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza (the Shah of Iran), and others like them – fell when their arrogance reached its peak, and this one will fall too.”
富が超富裕層に集中、中間層以下は貧困化(有馬侑之介)
2023年の所得上位0.01%層の所得シェアは2.28%。アベノミクスが始まった2012年には上位0.01%の所得シェアは1.19%だったから、10年余りでおよそ2倍に拡大した計算になる。
所得上位層のシェア拡大は上位0.01%だけではない。上位0.1%は2012年の3.33%から2023年は4.83%へ、上位1%も2012年の10.5%から2023年は12.04%へと上昇した。一方、上位5%、10%、20%の所得シェアは横ばい、もしくは低下したという。
中間層や低所得層の貧困化が進んでいる。世帯の労働所得の中央値は1994年の537万5,000円から2019年には305万円へ低下した。2000年代以降の格差拡大を説明するうえで、中間層以下の所得減少は社会問題として重い意味を持つ。
ジニ係数は0.5855だった。調査を開始した1962年以降で最も高い水準だ。引退後で労働所得が少ない高齢者世帯の増加が数値を押し上げた一因になっているという見方もあるが、貧困化が進んでいるという見方が大勢を占めている。
死因
年末に母が死んだ。大腸にがんが見つかり、緩和ケアを始めてから71日。99歳の誕生日を迎え白寿を祝ってから2週間あまり。安らかな死だった。死亡診断書を書くためにやって来てくれた医師は「がんとか、まあいろいろありましたけれど、死因は老衰にしておきます」と言った。私は考えもなく「ありがとうございます」と言った。
「死因ががんだと、死んだ人がかわいそう」という考え方があるのを、私はあとで知った。「がんはかわいそう、老衰はめでたい」という、そんな考え方だ。がんはかわいそう、自殺はまずい。そんなことで死因が変わるのだとしたら、がんや自殺で死ぬ人の数は、統計よりずっと多いことになる。
それでも、統計上がんは日本人の死因の第1位で、4人に1人はがんで亡くなる。多くの人たちががんで死ぬわけだが、がんで死ぬのは、ほんとうにかわいそうなのだろうか?
日本人の死因の2位以下には、心疾患、老衰、脳血管疾患、肺炎、誤嚥性肺炎、不慮の事故などが並ぶ。果たして、そのうちのどれが、がんよりマシだというのだろう?
50年ほど前に「ぽっくり寺」が流行った。健康で長生きし苦しまずに最期を迎えたいという人たちが訪れたわけだが、「ぽっくり」は果たしていいものだろうか?
「ぽっくり」でまず浮かんでくるのは心筋梗塞だが、15分以上ものあいだ胸が締め付けられるような焼けるような痛みを全身に感じ、息切れ・冷や汗・吐き気・嘔吐・めまいなどとともに意識が遠のいてゆくという。くも膜下出血や脳出血では「バットで殴られたような」人生最悪の激痛を感じるそうだ。そんな「ぽっくり」がいいわけはない。
「ぽっくり」は突然の死だから、死の準備ができていない。隠しておきたいことも隠せず、しておきたいこともできず、死後に見られたくないものも残したままで死んでゆく。それはいやだ。
老衰で死ぬのはどうだろう。死のかなり前から全身が衰え、不如意と不自由と惨めさに長い間耐えたあとで、ようやく死を迎える。見たり聴いたりみ食べたりというような楽しみはなくってゆき、からだじゅうの痛みに耐え、寝たきりになって、下の世話はもちろん、陰部洗浄・口腔ケアなどを受け、心不全と筋力低下で身体は動かせず、呼吸も苦しく、言葉を発するのも無理というような状況になって死んでゆく。そこには、人間の尊厳など、かけらもない。私は老衰もいやだ。
事故や災害で死ぬのも、殺されるのも、自殺もいやだ。
となれば、がんで死ぬしか道はない。がんが見つったらすぐに緩和ケアを始め、医療用麻薬を適切に使ってもらって痛みを和らげ、便秘や吐き気などもなく安らかに死んでゆく。それがいい。
母が死んでからやって来て死亡診断書を書いてくれた医師は「死因は老衰にしておきます」と言った。その裏には「がん」は悲惨で「老衰」はめでたいという考えが見え隠れする。でも私には、悲惨とされている「がん」よりも、人間の尊厳というものがなくなって死んでゆく「老衰」のほうがずっと悲惨に思える。というか、選べるものならば、私は「がん」で死んでゆきたい。医療用麻薬を存分に浴びながら。
国家という暴力集団と民主主義という理想の物語(Copilot)
🔥 国家はなぜ暴力から生まれたのか
歴史を振り返ると、国家の起源はほぼ例外なく「暴力を組織化した集団」です。
農耕社会が生まれ、「富が蓄積される ⇒ それを奪う集団が現れる ⇒ 奪われないために武装する ⇒ 武装した集団が支配者になる」という循環が繰り返され、暴力を独占した集団=国家という構造ができあがった。
国家は“暴力の否定”ではなく、暴力の管理として誕生したのです。
🕊️ では、なぜ民主主義という「理想の物語」が必要なのか
国家が暴力を独占している以上、その暴力が暴走しないためには、暴力を正当化する物語が必要になります。
かつては「王権神授説」「血統」「宗教」「帝国の使命」などがその役割を果たしました。しかし現代では、それらは説得力を失った。そこで登場したのが「民主主義」という物語です。
民主主義は、国家の暴力を「あなた自身が選んだ代表が行使している」という形に変換することで、暴力の正当性を“市民の側に戻す”仕組みです。
つまり民主主義は、国家の暴力を“平和のための暴力”に変換するための物語だと言える。
🌱 民主主義は“理想”だからこそ必要になる
ここがとても重要です。民主主義は、完成した制度ではなく、現実を完全に反映するものでもなく、しばしば裏切られ、しばしば機能不全に陥る。
それでもなお、「平和であるべきだ」という理想を掲げ続ける唯一の物語なのです。
国家が暴力から生まれた以上、暴力を抑制し続けるためには、暴力を超える理念が必要になる。
その理念が、民主主義であり、人権であり、法の支配であり、平等であり、自由です。
民主主義は“現実の記述”ではなく、暴力を制御するためのフィクションなのだと思います。
しかし、そのフィクションがあるからこそ、国家は暴力をむき出しにせずに済む。
国家が暴力的であることは変わらない。だからこそ、暴力を抑え、平和を志向する物語が必要になる。民主主義は、その物語の中で最も人間の尊厳に近い形を持つものです。
そして、民主主義が“理想”であることは欠点ではなく、むしろその理想性こそが、国家の暴力を縛る力になる。
「民主主義という物語の力」をもう少し深く掘り下げるなら、次に考えるべきは「物語が弱まると国家の暴力はどう変質するのか」という点かもしれません。