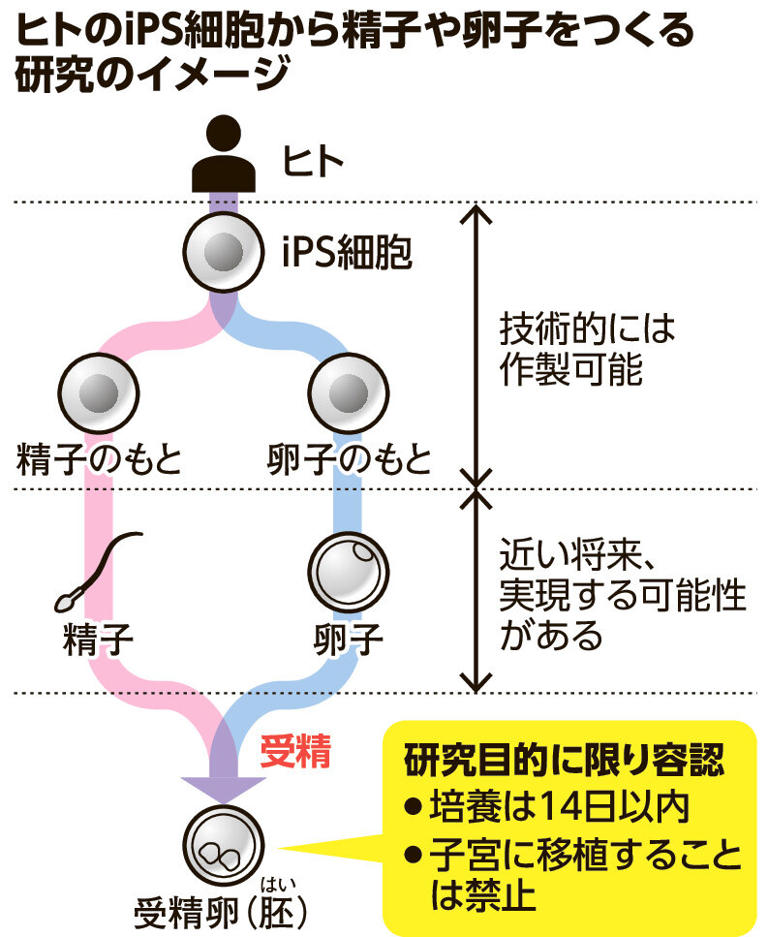Le jour où je me suis emparé de la langue française, j’ai perdu le japonais pour toujours dans sa pureté originelle. Ma langue d’origine a perdu son statut de langue d’origine. J’ai appris à parler comme un étranger dans ma propre langue. Mon errance entre les deux langues a commencé… Je ne suis donc ni japonais ni français. Je ne cesse finalement de me rendre étranger à moi-même dans les deux langues, en allant et en revenant de l’une à l’autre, pour me sentir toujours décalé, hors de place. Mais, justement, c’est de ce lieu écarté que j’accède à la parole ; c’est de ce lieu ou plutôt de ce non-lieu que j’exprime tout mon amour du français, tout mon attachement au japonais.
Je suis étranger ici et là et je le demeure.
 The KORAIL PASS allows foreigners visiting Korea to journey across the country by train at a reasonable price.
The KORAIL PASS allows foreigners visiting Korea to journey across the country by train at a reasonable price.