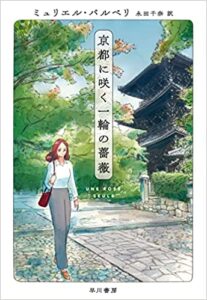2024年6月28日(金)
卓上の花も生きている
今週の書物/
『花のこころ―奈良円照寺尼門跡といけばな』
山本静山著、主婦の友社、1968年刊
サッカーの中継を興奮して見る。最近のテレビ中継は、リプレイもあって面白い。でも結局は、テレビ観戦の域を出はしない。画面に映らないことは見ることができないし、マイクが拾わない音は聞こえてこない。その場の雰囲気は感じられないし、暑いか寒いかすらもわからない。スタジアムにいないとわからないことは多い。
演奏会も展覧会も同じで、出かけて行かないと味わえない感動っていうものが間違いなくある。演奏者が演奏の合間に見せるはにかみの表情とか、演奏中のちょっとした仕草とかは、その場にいなければわからないし、美術作品の大きさや質感なども、作品を前にしなければ、わかりはしない。
朝、雨戸を開けて、遠くに見える山や空を眺め、庭にやってくる鳥や咲いている花を見て味わう小さな感動なども、写真や映像には変換できない。そもそも感動は、どう伝えようと、他人には伝わらない。自分にしかわからないもののような気がする。分かち合うことは難しい。
物理学者の Carlo Rovelli は「時間は存在しない」と言うけれど、時間は間違いなくあって、ひとりひとりが生きている限られた時間のなかで、自分にしかわからないことが、少なからずあるように思える。
谷崎潤一郎の『雪後庵夜話』の最初に出てくる歌「我という人の心はただひとりわれより他に知る人はなし」は、中学のサッカー仲間の手塚研一さんがその存在を教えてくれた歌だが、まさにそのとおりだと思う。憧れとか、寂しさとか、悲しみとか、喜びとかは、自分にしかわからない。
残りの短い時間のなかで、自分に正直になって、素直に、わがままにして、多くの感動を味わいたいと、生意気なことを考える。そんなことをしていれば、いつかはバチが当たるだろう。それでも、生きているあいだは、生きたい。
そんなことを考えていたら、部屋のなかに飾られた花が目に入った。地面から切り離され、土を纏うこともなく、少しの水を与えられ飾られている卓上の花は、いったい何を感じているのだろう。
で今週は、花についての一冊、『花のこころ―奈良円照寺尼門跡といけばな』(山本静山著、主婦の友社、1968年刊)だ。私の家の本棚には、山本静山の本が 4冊並んでいる。いずれも主婦の友社から出版されていて、年代順に『花のこころ (1968年)』『花のすがた (1973年)』『花のむれ (1981年)』『花のながれ (1992年)』。『花のこころ』だけが山本静山が書いた本という感じで、あとの 3冊は 山本静山によって生けられた花の写真集という作りの本だ。とはいっても、4冊とも素晴らしく、好きな本が並ぶ本棚に置かれている。
山本静山は、『昭和天皇の妹君: 謎につつまれた悲劇の皇女』(河原敏明著、ダイナミックセラーズ出版、1991年刊)によれば、三笠宮の双子の妹だったというが、真実は誰にもわからない。わかる必要もない。わかっているのは、十世圓照寺門跡住職としての役割を果たし、山村御流家元としていけばなを極めた人ということで、昭和天皇の妹であったかどうかなどということは、知る必要はない。
山本静山が始めた山村御流は、ひとことで言えば「野に咲いているように生ける」。そのことに尽きる。もっとも、そんなことが集まってくる人たちに伝わるはずもなく、いま巷にある山村御流にとって大事なのは、師事であり、免状であり、もっと言えば、華美であり、虚飾である。そんなことを思わせるほど『花のこころ』は、そしてそれを書いた山本静山は、自然に近い。
大和には 3つの尼門跡があるという。門跡は皇族・公家が住職を務める特定の寺院(あるいはその住職)のことで、法隆寺と僧寺・尼寺の関係にあった中宮寺門跡、総国分尼寺だった法華寺門跡、そして奈良の南東 4kmのところにある円照寺門跡がこれにあたる。
尼門跡には一般の尼寺にはない特別な行儀作法があり、活動にもいろいろな制約がある。そのなかで、いのちについて考え続け、野の花や草を生け続けてきたのだから、生けられた花には、自然の持つ力が溢れている。
山本静山の言葉を少し紹介する。
秋の千草がにおっている野や山のほとりには、点々と小松が美しい緑を輝かせながら生えています。一方、秋の野を飾る七草の葉や茎は、松のように深い緑の色ではなくて、こがねなす秋の色をたたえています。その輝くような色で、この秋を限りにと生きる七草と、小さいながらにも力強く、やがては大空へとそびえたってゆく松の緑との対照は、味わいがあります。美しい調和でもあり、必然の美であると思います。
自然を眺める目が独特なのに気がつく。
人間の世界には、ずいぶんとむだが多いように思えますが、そのむだが、なかなかたいせつなのです。 山へ登り、野にさまよい、または旅の車中から、ただ何とはなしに、あたりの風景をながめている。そのなにげなくながめているということが、数多く重なってゆくにつれて、自然の美しさ、草や木の在り方が、心の目に写されてゆくのです。そうして花を生けるときに、いつとはなしにそのことが、大きく役立っていることに気がつきます。おもしろいことです。
おもしろいことですという山本静山の顔が、浮かんでくるようだ。
本のなかで、山本静山は、「花へのこころが、美しい自然の姿とともに、いつまでも清く、かぐわしく、人の世のつづく限り、咲きつづき、人によき幸を与えてくれますよう、花に祈りつつ」などという恥ずかしくなるような文章とともに、「花は野にあるように———」という言葉を繰り返す。こんなことをてらいなく書くなんていうことは山本静山にしかできない。
この本のなかでは、春夏秋冬は何よりも重要で、その変化は特別な意味を持つ。ただ、四季は円照寺のまわりの自然の四季で、カレンダーに書かれた四季でもなければ、季語などといって決められた四季でもない。実際に外に出て花を摘み草を摘みして感じた四季は。どんな四季よりリアルだ。、
季節感あふれる本の作りと山本静山という人とが、不思議と合っている。作られてから56年という時が経っているというのに、書かれていることはみずみずしい。ゆっくりと読むにふさわしい本に久々に出合った気がした。
本から目を上げ、改めて卓上の花を眺める。卓上の花が、私に話しかける。そう、飾られている花は、間違いなく生きている。