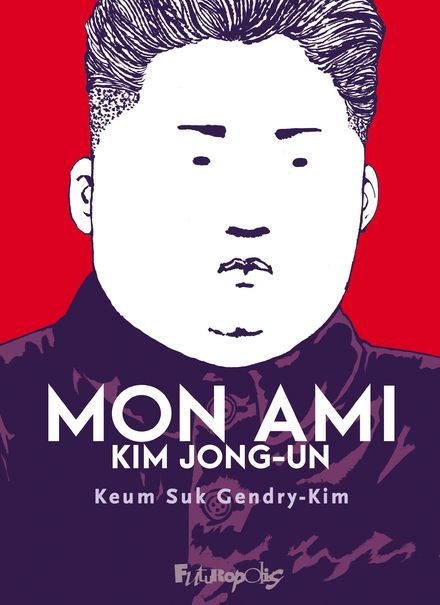The rise of end times fascism (Naomi Klein and Astra Taylor)
The governing ideology of the far right has become a monstrous, supremacist survivalism. Our task is to build a movement strong enough to stop them.
Though it builds on enduring rightwing tendencies … we simply have not faced such a powerful apocalyptic strain in government before.
End times fascism is a darkly festive fatalism – a final refuge for those who find it easier to celebrate destruction than imagine living without supremacy.
The forces we are up against have made peace with mass death. They are treasonous to this world and its human and non-human inhabitants.
Liberty Island
Climat, de la confusion à la manipulation (Daniel Husson)
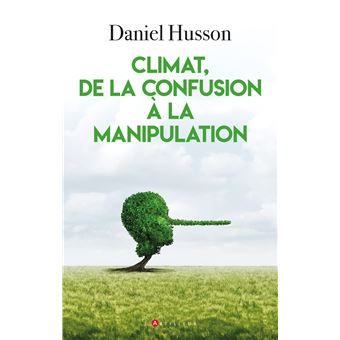 Écrit dans un style aussi alerte que pédagogique, l’ouvrage ouvre le feu sur la peur savamment entretenue de l’arrêt prochain du Gulf Stream, cette vieille scie régulièrement ressortie par les médias pour varier un peu le récit millénariste sur le CO2. L’auteur en profite pour rappeler que l’atmosphère et l’océan ne boxent ni de près ni de loin dans la même catégorie, et qu’il faut une sacré méconnaissance des ordres de grandeurs pour croire que la première pourrait dominer le second et l’influencer de façon majeure. Parmi les autres sujets abordés mentionnons la notion de rétroaction (souvent positive dans les discours de peur exponentielle, mais bien plus souvents négatifs dans la vraie vie et ses phénomènes d’atténuation), la physique de l’effet de serre (expliquée sans pathos ni technicité inutile) ou encore la pertinence (discutable) des modèles de circulation générale.
Écrit dans un style aussi alerte que pédagogique, l’ouvrage ouvre le feu sur la peur savamment entretenue de l’arrêt prochain du Gulf Stream, cette vieille scie régulièrement ressortie par les médias pour varier un peu le récit millénariste sur le CO2. L’auteur en profite pour rappeler que l’atmosphère et l’océan ne boxent ni de près ni de loin dans la même catégorie, et qu’il faut une sacré méconnaissance des ordres de grandeurs pour croire que la première pourrait dominer le second et l’influencer de façon majeure. Parmi les autres sujets abordés mentionnons la notion de rétroaction (souvent positive dans les discours de peur exponentielle, mais bien plus souvents négatifs dans la vraie vie et ses phénomènes d’atténuation), la physique de l’effet de serre (expliquée sans pathos ni technicité inutile) ou encore la pertinence (discutable) des modèles de circulation générale.
Parthenogenesis (Corryn Wetzel)
In some very rare cases, animal species reproduce via parthenogenesis exclusively. One such species is the desert grassland whiptail lizard, all of which are female.
The ability to reproduce asexually allows animals to pass on their genes without spending energy finding a mate, and so can help sustain a species in challenging conditions. If a Komodo dragon arrives on an uninhabited island, for example, she alone could create a population through parthenogenesis.
However, because every individual would be genetically identical, Komodo dragon mothers and their daughters would be more vulnerable to disease and environmental changes than a genetically-varied group.
Panifico
A Better Way to Defend America (Stephen Peter Rosen)
Discussions of U.S. defense posture should begin by asking not who is virtuous but what does the world look like now and what will it look like in the future. Given the dramatic shifts in the global economy in recent decades, as well as the transformation of nonnuclear weapons capabilities and the rise of space-based sensors, it is clear that the defense posture that the United States established 75 years ago is no longer appropriate or adequate. The United States should look beyond its current disputes with its allies and ask how it can better situate its forces to protect core U.S. national interests in a more dangerous world.
DEI (Elon Musk)
End of Human Rights?
There is no doubt that the human rights movement is facing the greatest test it has confronted since its emergence in the 1970s as a major participant in the international order.
中国の資産家が東京駅の超高層ホテルから《江戸城全景》を見下ろし興奮した「意外な理由」
| 織田信長 | 鳴かぬなら殺してしまえホトトギス | トランプ | 銭 |
| 豊臣秀吉 | 鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス | プーチン | 地 |
| 徳川家康 | 鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス | 習近平 | 権 |