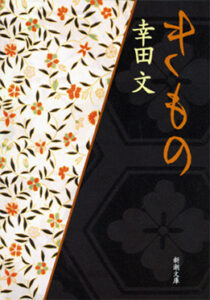2023年12月15日(金)
男にはうかがい知れない女の会話
野坂昭如に言われるまでもなく「男と女のあいだには 深くて暗い河がある」ようで、時折、女たちの会話が理解不能に思える瞬間が訪れる。身近な人のうわさ話、贈答品のことなどなど、しなくていい会話や、意味不明の会話が延々と続くとき、耳がほとんど閉じている自分に気づく。話して何かを得ようとか、何かを解決しようとか、そういうことではない。話すこと自体が目的なのか。世間体を気にする割には、会話は社会的な広がりを持たない。
そんな日本の女たちの会話を理解するとっかかりになるのが、幸田文の『きもの』である。最初のページの胴着の話から、最後のページの寝巻のところまで、とにかく違和感が付きまとう。
幸田文は幸田露伴の娘で、結婚、出産、離婚を経て父のもとに戻り、露伴の死後に文筆家になった。娘の青木玉、孫の青木奈緒も文筆家。四代にわたって文筆家になっている。とはいっても、幸田文自身に自分が文筆家だという自覚があったわけではないようで、幸田文について調べてみると、露伴の死後の2~3年に『雑記』『終焉』『父』『こんなこと』『みそっかす』などを出版すると、昭和25年には断筆宣言をして柳橋の芸者置屋の住み込み女中になったりとか、昭和40年からは焼失した法輪寺三重塔の再建に走り回ったりとか、文筆がプライオリティーでないという生涯が見えてくる。
『きもの』は、法輪寺三重塔の再建に走り回るなかで『闘』と同じ時期に執筆され、三年にわたって「新潮」に発表された。だから、話の中に出てくる人たちは大正の頃の人たちだとしても、幸田文のまわりの人たちは、みんな戦後の復興とか経済成長とかのなかにいたことになる。
大正・昭和の人たちの持っていた不自由さは、違和感というよりは異和感といったほうがいいような、私たちには理解できない不自由さで、世間体にしろ、行儀にしても、誰から押し付けられたものでなく、自分で自分を規制する不自由さなのだ。
主人公のるつ子は、間違いなく幸田文自身なのだが、『きもの』には私小説らしさがない。幸田文自身が欲しかった自由とか自立とかは、青木玉や青木奈緒にとっては当たり前のもので、欲しがるものではなかっただろう。でも、幸田文には切実なもので、だからこそ、これまでかこれまでかというほどに、自分のまわりのことばかりを書き連ねたのではないか。
自由とはいっても、放縦とか放埓とかとは一線を画したい。また、豊かになるとはいっても、優しさや親しみを忘れたくない。そんなことが垣間見られる幸田文の文章からは、幸田文が譲りたくなかった品とか感性とかが見て取れる。
それにしても、狭い社会のなかに登場する人物たちの、なんと俗物的なことか。日本が開発途上国であったからという説明だけでは済まされない、戦後の荒廃の様子が見て取れる。そしてその荒廃は、戦後何十年経っても、延々と続いている。『きもの』は、そんなことを感じさせてくれる一冊だ。
話を「日本の女たちの会話」に戻そう。近頃は、身近な人のうわさ話をする人は少なくなった。その代わり、メディアに登場する人のうわさ話をする人が増えている。根源は同じ。自分の「人に対する評価」が、みんなの「人に対する評価」と一致しているかを確認したいのではないだろうか?
「あそこの家の娘さんは毎晩のように遊び歩いて」というのが「あの政治家が不倫をして」になったとしても、「けしからん」を共有したいという欲望は変わらない。ネット上の女性週刊誌ダネが男にはそれほど面白くないのは、一昔前の井戸端会議に男が興味を示さなかったことと同じに思える。
幸田文の生涯にわたる数々の文章が、身近な人や身近なことで成り立っていたのは、決して偶然ではないし、それは決して悪いことばかりではない。ただ、幸田文が美しいと思ったものの多くが消えつつあるのは残念としか言いようがない。