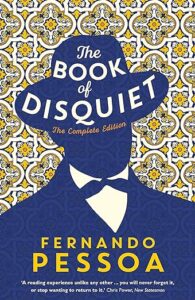2024年2月2日(金)
弱者により添う素朴な作品たち
今週の書物/
『Le Roman du Lièvre』
Francis Jammes 著、Mercure de France、1922年刊(Wikisource)
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Roman_du_Lièvre
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes
1970年3月、雑誌「an-an ELLE JAPON」の創刊号が発売された。表紙はモデルの Marita Gissy、その上に「an・an」「ELLE JAPON」「創刊号」「3 20」といった文字と パンダのロゴが並んでいる。三島由紀夫、澁澤龍彦、片山健、大橋歩といった名前のなかに、アンアン代表の立川ユリの名前がある。ビートルズが起用された広告とか、ELLEの社長のおめでとうメッセージとか、何から何までが衝撃だった。
その年の8月5日号の「an-an No.10」に、フランシス・ジャムの『パイプ』が載った。翻訳は澁澤龍彦、片山健のイラストが添えられている。短い物語のなかに、「若者」が「青年」になり「老人」になって死ぬまでのことが描かれる。「若者」の父母が死ぬ。リンゴのような胸を持つ美しい妻が外見のいい男と寝ているのを見て「青年」は何も言わずに家を出る。大都会で一緒にいた犬が死に「老人」も死ぬ。それだけの話なのだが、なぜか胸に迫った。
9月20日号の「an-an No.13」には、フランシス・ジャムの『神様の慈愛』が載った。翻訳が吉村啓喜、解説が澁澤龍彦、イラストは片山健。一匹の牝猫と暮らしていた平凡な娘が、男に捨てられる。娘は妊娠し、牝猫も身ごもる。ある日、男から手紙と25フランが送られてくる。娘はその金でコンロと炭とマッチを買って自殺する。神さまは、天国に着いた娘と雌猫のために部屋を用意してくれ、娘は女の子を産み、雌猫は4匹の仔猫を産んだ。そういう話が、とても新鮮に感じられた。
「an-an」にはその後も片山健のイラストがついた物語が載った。そして私の頭の中にはフランシス・ジャムの名前が残った。この話をすると、「澁澤龍彦の魔術にかかったのだ」と言われたり、「なんでそんなつまらない話に感激してるんだ」と言われたりした。でも私には、フランシス・ジャムの物語は、つまらない話ではなかった。
その後、フランシス・ジャムの詩に出会うことがあった。フランスの学校に通うようになった娘がフランシス・ジャムの詩を暗唱していたのだ。もう時代遅れになっていたフランシス・ジャムが、学校のなかで生き続けていたのである。
ただ、フランシス・ジャムの詩は、学校で暗唱させるだけあって、どれもつまらない。あの「an-an」に載ったキラキラした物語たちからは程遠い。なぜかなと思って『パイプ』や『神様の慈愛』を探してみると、フランシス・ジャムの『Contes(コント集)』にたどり着いた。
『Contes』のなかには、『La Pipe(パイプ)』も『La Bonté du Bon Dieu(神様の慈愛)』もある。確か「an-an」に載っていた『Le tramway』もある。『Le Paradis』もある。読んでみると、やっぱりいい。「an-an」で読んだのと同じ読後感。同じように優しい気持ちになるではないか。澁澤龍彦や吉村啓喜の魔術ではなく、フランシス・ジャムの魔術だったのだ。
そんなわけで今週は、そのフランシス・ジャムの短編集を改めて読んでみる。『Le Roman du Lièvre』(Francis Jammes著、Mercure de France、1922年刊)だ。著者は1868年生まれ。スペインとの国境に近いフランスのオート=ピレネー県で生まれ、パリから遠く離れた場所でパリの潮流とはまったく関係のない文筆活動を続けた。そんなフランシス・ジャムの「弱い者たちに向けられる目線」が形作る作品世界を味わってみる。
この頃、フランスにはまだ身分制度が残っていた。『Le tramway』というコントに、それがよく描かれている。働き者の夫と、優しい妻と、幼い娘が、乗合馬車に乗ろうとお金を用意して道に立った。ほとんど誰も乗っていない乗合馬車が近づいてきたので、働き者の夫は運転手に止まるよう合図を送った。ところが運転手は、この3人を軽蔑の目で見て、乗合馬車を止めようとはしなかった。乗合馬車に乗ろうというウキウキした3人の気持ちが一瞬にして砕かれる。そんな気持ちの描写はまったくないのだが、口惜しさや悲しみが伝わってくる。
フランシス・ジャムは、今では考えられないくらい信仰心が強く、書かれる神さまは想像の域を超えている。例えば『Le Paradis』のなかに描かれる神さまは「ひとつの袋のなかにひとかけらのパンしか持っていない人たち」や「署名の仕方を知らないがために逮捕され収監されている人たち」のような姿をしている。それでいて「奉仕することとか、与えることとかが、幸せなのだ」と柔らかい声で話し、微笑みを絶やさない。今の世の中でそんな神さまのイメージがどれほど通じるのか。信仰心も、時代とともに変わってゆくのだろうか。
描写は時に異常なほど細かくなる。先ほど触れた『La Bonté du Bon Dieu』の冒頭が、そのいい例だ。
彼女は可愛らしいきゃしゃ華奢な娘だった。彼女はある店で働いていた。彼女は、あえて言うなら、格別に聡明だというわけではなかったが、優しくて黒い目をしていた。その目は少し悲しそうに人に向けられ、その後で伏せられるのだった。彼女は情愛は深いが平凡な娘であると思われていた。そう思われたのは彼女のとても優しい平凡さのせいだった。そしてこの平凡さは真の詩人だけが理解できるもので、そこには人への憎しみは全くみられないのだった。
彼女はその住んでいる部屋と同じように質素な娘であると思われていた。彼女は人にもらった1匹のかわいい牝猫だけがいる簡素な部屋にひとり暮らしをしていたのだ。毎朝、店に出かける前に彼女はお椀の中に少量のミルクを入れておくのだった。
どうだろうか。短い物語をこのように始めるフランシス・ジャムの性格が見えてくるではないか。
『Le Roman du Lièvre』は、人間の狩りから逃れて走るウサギの描写から始まる。人が作った道を横切り、馬や犬や鶉に出会い、山を眺め、川を眺め、走り続ける。疲れ果てたウサギは居眠りをする。しかし夢の中でさえ休むことはできない。ほんのわずかな物音でも、動くもの、落ちるもの、ぶつかるものすべてが危険を知らせる。
私が好きな『Contes』以外にも、読みどころがたくさんある本だ。今回はじめて、そう気づいた。時代遅れのフランシス・ジャムの文章がいいと思えるのは、私が時代遅れになったからではないか。ふと、そう思った。