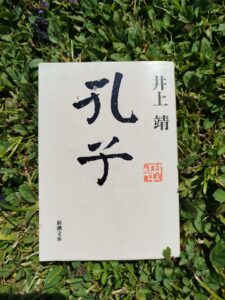2024年8月30日(金)
次は何が起きるんだろうと思わせる文章
今週の書物/
『Perfume』
Patrick Süskind 著、John E. Woods 訳
Penguin Books、1986年刊
オフィスで電子機器に囲まれて多くの時間をすごしていれば、五感を意識することはあまりない。ところがスクリーン上の情報や書類、ミーティングなどから解放され、自然を意識して暮らしてみると、やたらと五感を感じる。
朝起きて雨戸を開け、朝の空気を感じる。朝のひかり、小鳥のさえずり、葉についた水滴、花の香り。そうしたものに囲まれて一日を始めれば、その日は間違いなく良いものになる。暑さ寒さを感じ、汗をかいたり凍えたりすることの、どれだけ気持ちいいことか、
そんな五感だが、目が見えなくなったり、耳が聞こえくなったりすれば、暮らしがむずかしくなる。痛みを感じなくなったり暑さ寒さを感じなくなれば危険だし、新型コロナに感染して味覚を失えば食べることや飲むことに支障がでる。逆に、見え過ぎたり、聞こえ過ぎたり、感じ過ぎたり、味覚が良過ぎたりするとどうなるか。
もうずいぶん前になるが、自らを「nez(ネ)」と紹介するフランス人の家を訪れたことがある。よくよく聞いてみると、香水の会社に勤める調香師で、匂いの専門家。パリとかニューヨークといった大都市は嫌な臭いでいっぱいで住むことができず、山に囲まれた田舎に住んでいるという。鼻がいいというのは、いいことばかりではないのだと、その時はじめて知った。
見えすぎも聞こえすぎも、人によっては困ることがあるのかもしれない。見えなくてもいいものが見えてしまったり、聞こえなくてもいい雑音が聞こえ続けるのはつらいだろう。舌が肥えて普通の食べ物がおいしく感じられないのはいやだろうし、高いワインしかおいしく感じられないなんて不幸でしかない。
五感の個人差は大きい。よく、人と動物とでは見ているものが違うという。人は目の前のものを色と形で見ているが、犬は通ることのできる道や座ることのできる場所を、蠅は照明と食器や食べ物を見ている。自分にとって重要なものしか見ていないのだ。
人も、自分が見たいものばかり見て、聞きたいものばかり聞いているのではないか。嗅ぎたい匂いばかりを嗅ぎ、好きな味の食べ物や飲み物ばかり選び取っているのではないか。自分の五感は、隣の人の五感と違う。そう考えると、五感というものがやけに魅力的に感じられる。
五感についての文章は多い。視覚に訴える文章が写真や映像を超えるのは難しいし、聴覚に訴える文章が実際の音や録音の再生を超えるのも難しい。触覚を表現する文章にはあまりお目にかからないし、味覚を表現する文章には陳腐なものが多い。
嗅覚に関する文章は昔からあり、源氏物語の匂宮の「また人に 馴れける袖の 移り香を わが身にしめて 恨みつるかな」なんていう歌を持ってくるまでもなく、平安時代の歌の世界は人の香りや花の香りであふれている。
で今週は、匂いに特化した小説を読む。『Perfume』(Patrick Süskind 著、John E. Woods 訳、Penguin Books、1986年刊)だ。とても特異な作品だ。
この小説は、最近の商業的な小説に見られるような勢いよく一気に書かれたものとはまったくといっていいほど違う。18世紀のフランスのこと、そして匂いのことなどが、じつに見事に描かれている。作者はミュンヘンとエクス・アン・プロヴァンスで中世史と近代史を学び、パリとミュンヘンで ラジオの脚本や小説を書いていた。その経験がこの一冊に凝縮している。
まず驚くのが、18世紀のフランスの汚なさだ。人々は不潔で、街は悪臭を放っている。登場人物の匂いは、臭いと書いたほうがいいものが多く、体の匂い、汗の匂い、仕事に関連した匂い、住環境に関係する匂い、そして新鮮な花の香りやアロマの香りなどが詳細に描かれ、どのページからも匂いが漂ってくる。
パリの中心部の露店市場で魚を売っていた主人公の母親は、赤ん坊を産み落とすと、すぐに赤ん坊を魚の頭や尻尾と共にゴミのなかに捨てた。ゴミの中から見つけられた主人公からは匂いがしなかった。そんなふうに始まる小説からは、本当に匂いがしてくる。
また、母親が生まれたばかりのグルヌイユを殺そうとする最初から、グルヌイユが死ぬ最後まで、死が身近なものとして描かれていることにも驚く。18世紀のフランスの社会は、現代から見ればはるかに暴力的で、貧しい。それなのに、誰もがそんな社会をあたりまえのこととして受け入れてくる。
さすがラジオの脚本を書いた人だと感じるのが、「次は何が起きるんだろう」と思わせるところだ。たとえば、主人公のグルヌイのがある日、通りで、これまで嗅いだことのない香りを感じ取る場面。まだ嗅いだことのない極上の匂いに気付き、その匂いを追ってゆくところは、圧倒的だ。
さまざまな匂いが混じりあったパリの通りを、いい匂いがしてくるほうに向かってゆく。街の臭いに圧倒され、時にいい匂いの方向を失いながら進む。読みながらグルヌイユを応援している自分に気付く。やがてグルヌイユは、そのいい匂いのもとにたどり着く。その匂いが、赤毛の少女が発する香りだったということがわかる。そして、グルヌイユは、匂いを得るために少女を殺す。この殺人は唐突だ。
そこからのグルヌイユの人生は、苛酷だ。至高の匂いを手に入れようとする人生。香水屋に雇われて香水の調合を覚え、どんな香りでも作り出すことができるようになったグルヌイユは、パリを出て南に向かう。人に嫌悪感を感じたグルヌイユは、文明を避け洞窟で暮らす。野生の植物と動物とで生き延び、7年後に洞窟を出る。モンペリエでは、まわりにある手に入るものから自分の匂いを作り出し、その匂いを纏うことで他人から受け入れられる。
匂いのしない他人に嫌われる人間から、いい匂いのする他人に好かれる人間に変わることに成功したグルヌイユは、匂いを味方につけることで、侯爵の庇護を得るなどするが、人がいかに簡単に騙されるかを見て、人に対する憎悪感は軽蔑に変わる。そのあたりの感情は、作者自身の感情が書かれているのではないかと思うほど、見事に書かれている。
その後グルヌイユは、どうしたら自分が作り出した香りを閉じ込めて保存することができるかを知るために、グラースに向かう。グラースでは、24人の若い女性を殺し、人の香りを保存する方法を身に着け、最後にパリで殺した少女と同じ匂いを持つ少女を殺してその香りを閉じ込めることに成功する。
殺害容疑で警察に逮捕されたグルヌイユは死刑を宣告されるが、町の広場で処刑される直前に、少女の匂いから作った新しい香水を撒く。その香りはすぐに群衆を畏敬と崇拝の念で魅了し、有罪の証拠はそろっているのに、人々はグルヌイユの無実を確信し、判事は死刑判決を覆し、釈放を決める。このあたりの書き方は、秀逸だ。
人々は匂いによって狂い、欲望に包まれ、全員が集団乱交に参加するが、その後誰もそのことを口にせず、覚えている者はほとんどいない。捜査が再開され、グルヌイユの雇い主が犯人ということで絞首刑に処せられ、街は平穏を取り戻す。
グラースでの経験は、グルヌイユに人に対する憎悪感と軽蔑とを再認識させ、パリに戻って死のうという気持ちをもたらす。生まれた場所にたどり着くと、極上の香水を自分ふりかける。まわりにいた人々は香りに惹かれ、グルヌイユに集まってきて、バラバラにして食べてしまう。
パリの墓地の隣の魚市場で生まれ、オーベルニュでの洞窟生活を経て、グラースでの少女連続殺人と広場での奇跡、そしてパリに舞い戻ってのグルヌイユの昇天まで、まるでイエス・キリストの生涯をなぞったかのような物語なのだが、感情の欠如と倒錯ととらえられかねない行動とがイエス・キリストとの比較を拒む。でも、人々の心を満たす絶対的なものをつくりだした点は同じだし、愛のない孤独に耐えていた点もそっくりだ。
目的を達成しても空虚で、幸せは見つからず、死へ向かう。人から匂いを奪うために必要なテクニックをマスターし、人の匂いをまわりのものから作り出すこともできるようになったグルヌイユにとって、少女の匂いを手に入れたいという欲望が、殺人になってしまった。欲望はいつもおそろしい。